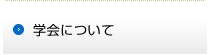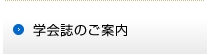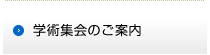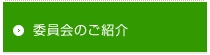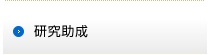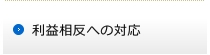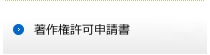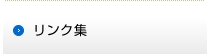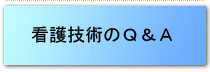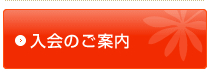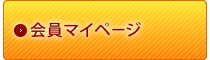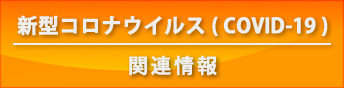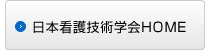移動動作評価
| グループ長 | 西田直子(京都先端科学大学 健康医療学部 看護学科) |
| メンバー |
水戸優子(神奈川県立保健福祉大学 保健福祉学部 看護学科)
國澤 尚子( 埼玉県立大学 保健医療福祉学部 看護学科)
若村 智子(京都大学 医学部 人間健康科学科)
平田美和(東京医療保健大学 看護学部 看護学科)
冨田川智志(滋賀医科大学 医学部)
首藤英里香(札幌医科大学 保健医療学部 看護学科)
小林由実(社会福祉法人 みなと舎 ゆう)
|
活動目的
患者が安全・安楽に移動動作を行うための患者の行動や看護師の援助方法の工夫について、科学的に分析するための研究・調査を行うことを目的とする。
活動計画と報告
| 計画 | 報告 | |
|---|---|---|
| 平成31年度 |
|
|
| 平成30年度 |
|
|
| 平成29年度 |
|
|
| 平成28年度 |
|
平成28年5月に移動動作評価グループ会議を行った。平成28年6月に第14回学術集会の交流セッションの評価をもとに「移動動作ガイドラインの展開例」のアセスメント、ケア評価、ポイント、フローチャートおよび動画の妥当性について検討し、第15回学術集会の交流セッションの内容と進行について協議した。
そこで、助言を受けた内容、シナリオの訂正を行い、平成28年8月にDVDの再撮影を計画した。
また、第15回学術集会の交流セッションの抄録に関してメール会議を行った。第15回学術集会の交流セッションで発表する調査結果報告を検討し、第15回学術集会の交流セッションで「移動動作ガイドラインの展開・アルゴリズム例」のフローチャートの改訂版とDVDの評価結果を報告した。
現在、フローチャートの改訂版とDVDの評価結果の修正と編集中である。
平成29年3月に日臨技医療政策企画の「病棟業務に必要な能力開発実践研修会」の講師として代表に送る予定である。
|
| 平成27年度 |
1.文献検討
1) 過去の移動動作に関する文献について調査する。
2) 文献を整理して、より安全・安楽に移動するための看護援助の工夫について検証方法を調べる。
2.第14回で「移動動作ガイドラインの展開例」(仮)の企画・運営を行う。
3.『移動動作のガイドライン』に基づいた移動動作の介助アルゴリズムを作成する。
|
平成27年4月に移動動作評価グループ会議を行い、第14回学術集会の交流セッションの内容と進行について協議し、補助具を用いた12パターンの移動・移乗動作を撮影した。
6月に第14回学術集会の交流セッションの抄録に関してメール会議を行い、撮影した内容の検討を行った。
8月に撮影した画像の整理とDVDを作成し、移動・移乗動作のアルゴリズム案の作成をメール会議により意見交換し内容を検討した。
平成27年10月に第14回学術集会の交流セッションで、移動・移乗動作のガイドライン案の背景およびアルゴリズム案による補助具を使用した移乗・移動方法についてDVDを用いて報告した。90名の参加者から様々な意見が出され盛況であった。本交流セッションで報告に用いたDVDは参加者に配布した。その後、交流セッションの内容を評価し、報告文を作成した。
|
| 平成26年度 |
1. 文献検討
1) 過去の移動動作に関する文献について調査する。
2) 文献を整理して、より安全・安楽に移動するための看護援助の工夫について検証方法を調べる。
2. 実態調査
過去の移動動作に関する調査をもとに内容を検討し調査したことをまとめる。移動補助用具について、文献とインターネットを用いて種類、価格、特長、対象条件などを調べ、整理する。
3. 第13回で「看護師の移動動作の実態と改善」(仮)の企画・運営を行う。
4. 『移動動作のガイドライン』を作成する。
|
平成26年4月29日の移動動作評価グループ会議を行い、第13回学術集会の交流セッションの内容と進行について協議し、さらに抄録に関してのメール会議を行った。
平成26年6月22日~25日オランダで開催されたNETNEP(国際看護教育学会)において、平成24年度に行った日本の移動動作の現状とガイドラインおよび教育の必要性についてポスターおよび口頭にて学会発表を行った。
平成26年8月に看護の移動・移乗介助に関する文献検討を行い、カテゴリーごとに整理した。さらに文献を絞り込み、12月~1月にかけて概念分析の手法を用いて再カテゴリー化し、全体を整理中である。
第13回学術集会の交流セッションで「移動動作ガイドラインの必要性と展開例」、改訂新・職場における腰痛予防対策指針「福祉・医療分野等における介護・看護作業」の概要説明、看護職の移動動作への意識や傾向の実態、移動動作のガイドラインの必要性および移動動作のガイドラインの一案の実演と画像を報告し、参加者は50名であった。
現在、『移動動作のガイドライン』の作成に向けて検討している。
|
| 平成25年度 |
1.文献検討 1)過去の移動動作に関する文献について調査する。 2)文献を整理して、より安全・安楽に移動するための看護援助の工夫について検証方法を調べる。 2.実態調査 過去の移動動作に関する調査をもとに内容を検討し調査したことをまとめる。移動補助用具について、文献とインターネットを用いて種類、価格、特長、対象条件などを調べ、整理する。 3.第12回で「看護師の移動動作の実態と改善」(仮)の企画・運営を行う。 4.『移動動作のガイドライン』を作成する。 |
平成25年6月に第12回学術集会の交流セッションの進行に関するメール会議を行った。 平成24年7~8月に200床以上の病院を対象に「看護職者による患者の車椅子移乗介助動作ガイドライン作成に向けた基礎研究」として実態調査を行い、8月に第12回学術集会の交流セッションで発表する調査の自由記述の整理を行った。 第12回学術集会の交流セッションで「看護師にとっての安全安楽な移動動作の援助の改善」を行い、50名の参加があった。内容をHPに報告した。 |
| 平成24年度 |
1.文献検討 1) 過去の移動動作に関する文献について調査する。 2) 文献を整理して、より安全・安楽に移動するための看護援助の工夫について検証方法を調べる。 2.実態調査過去の移動動作に関する調査を もとに内容を検討し調査する。 3.第11回で「看護師の移動動作の方法と工夫」(仮)の企画・運営を行う。 4.『移動動作のQ&A』の作成に向 け、準備を行う。 |
平成24年7月に第11回学術集会の交流セッションの進行と移動動作に関する調査の打ち合わせ会議を行った。全国200床以上の病院を系統的標本抽出法により抽出し、看護部長に研究協力の承認を得た後、調査票を郵送し、看護職者に郵送し、回答を得た。また、8月に第11回学術集会の交流セッションで使用するDVDの撮影とシナリオの検討を行った。 平成24年9月第11回学術集会交流セッションにおいて「看護師の移動動作の援助の実際と工夫」を行い、50名の参加者とともに活発な意見交換を行った。その内容は学会誌(第12巻第1号)に報告した。 |
| 平成23年度 |
1.文献検討 1) 過去の移動動作に関する文献について調査する。 2) 文献を整理して、より安全・安楽に移動するための看護援助の工夫について検証方法を調べる。 2.第10回学術集会の交流セッションで「看護師の移動動作の方法と工夫」(仮)の企画・運営を行う。 |
平成23年8月に第10回学術集会の交流セッションの進行に関する打ち合わせ会議を行った。 8月に第10回学術集会の交流セッションで使用するDVDの撮影とシナリオの検討を行った。 平成23年10月第10回学術集会交流セッションにおいて「看護師の移動動作の援助の実際と工夫」を行い、71名の参加があり、質疑応答が活発であった。その内容は学会誌(第11巻第1号)に報告した。 |
| 平成22年度 |
1.会議(7月、9月、12月)、ネット会議(1月、3月、5月、8月、11月) 2.会員への調査 1) 移動動作に関する実態について会員を対象に調査する。 2) 調査した内容を整理し、より安全・安楽に移動するための看護援助の判断や工夫について調べる。 3.学術集会交流セッションの企画・運営平成22年10月開催の第9回学術集会において「移動動作の現状について」という交流セッションを企画し、移動動作の援助の判断や工夫について交流を深め、討議する。 |
平成22年6月移動動作に関する実態について会員を対象に調査を行い、集計する。
平成22年7月グループ会議で調査の集計と分析を行い、交流セッションに向けての検討を行った。
平成22年10月看護技術学会において「移動動作の現状について」という交流セッションを企画し、昨年度のKJ法の報告、調査報告、教科書での記述の報告を行った。
平成22年12月末、学会誌9巻3号の報告、十周年記念誌の原稿の検討をメール会議で行った。
|
| 平成21年度 |
1.文献検討 2.第8回学術集会交流セッションの企画・運営 |
7月22日に交流セッションでの発表内容の確認と安全な移動動作の評価について困難な点を出して、KJ法を用いたグループワークを行うことを確認した。 9月26日第8回学術集会交流セッションを企画し、4演題の報告とKJ法による討議を行った。(参加者約20名) 10月11日グループ委員3名でKJ法による討議内容を整理した。 11月27日検討した内容のまとめと移動動差の困難に関する調査の検討を行った。 |